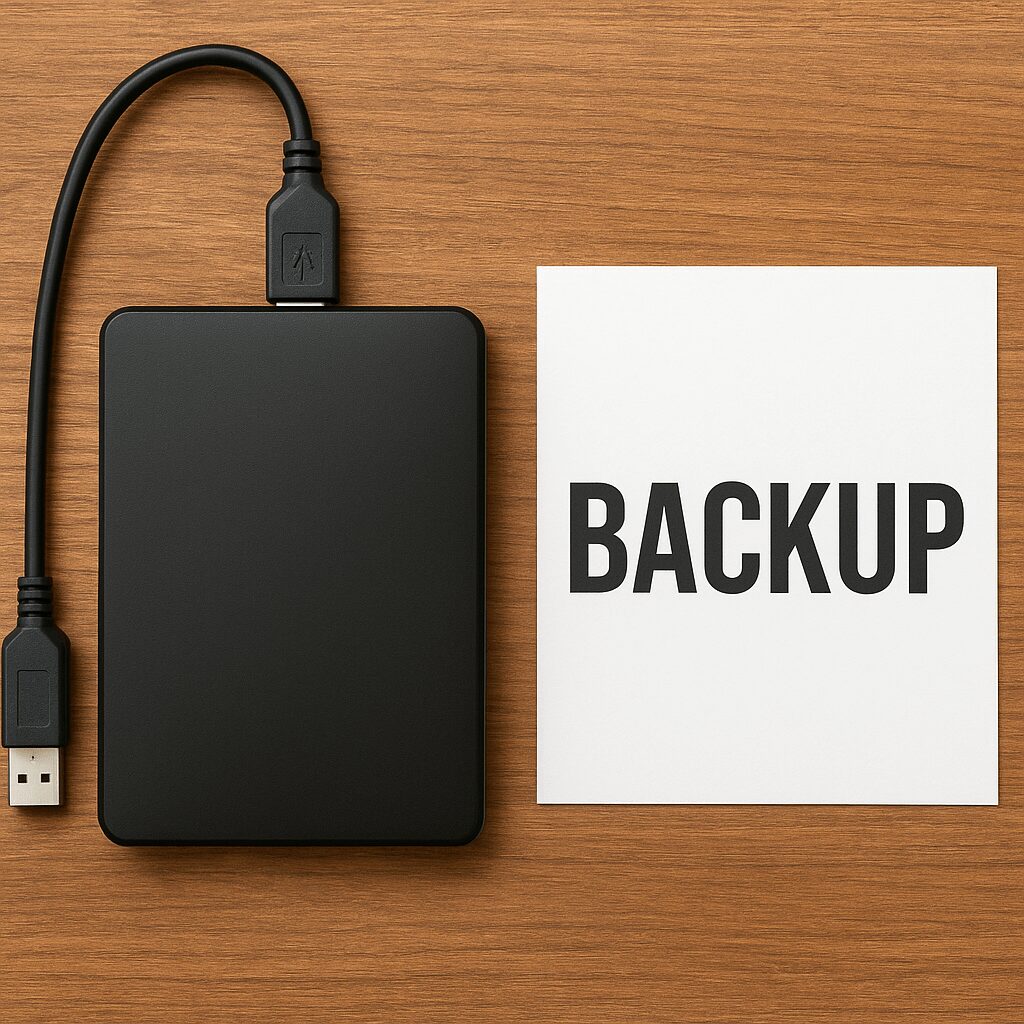
バックアップを取っていなかったために、大切なデータが消えてしまったという経験をしたことがある人は少なくないでしょう。トラブルや故障はいつ起こるかわからないため、定期的にバックアップを行うことをおすすめします。この記事では、バックアップの種類や効率的な進め方について解説します。
データのバックアップ方法は主に2種類
パソコン内の大切なデータをバックアップする方法は、主に次の2種類が一般的です。
個別でバックアップ
プライベートの大切な写真や連絡先、仕事に必要なデータや重要なメールなど、「これだけは保存しておきたい」と思うデータは人それぞれ異なります。パソコン内のすべてのデータをバックアップする必要がない場合は、保存したいものだけを個別にバックアップする方法があります。
全データをバックアップすると容量が大きくなることがありますが、個別でバックアップを行う場合は必要なファイルだけを選択するため、容量を抑えられるのがメリットです。
自動でファイルを保存する方法もありますが、手動で必要なデータを選ぶことで、バックアップ先の機器の容量を圧迫せずに済みます。一つひとつのデータを確認しながら作業するため手間や時間はかかりますが、バックアップ先の空き容量を確保しながらバックアップを取りたい場合に有効な方法です。
一括ですべてバックアップ
パソコン内のすべてのデータをバックアップしたい場合は、一括で丸ごとバックアップを行います。丸ごとバックアップでは、写真やメールなどのデータだけでなく、OSや設定、アプリもそのまま保存されます。
突然パソコンが故障した場合でも、すべてのデータをバックアップしておけば、バックアップ時点のOS環境まで含めて復元が可能です。ただし、容量が大きくなるため、使用する保存機器の容量には注意が必要です。
バックアップの際に役立つメディアの種類
パソコンのデータをバックアップするには、何らかのメディアを利用する必要があります。ここでは、バックアップに役立つメディアをいくつか紹介します。
HDDやSSD
HDDはバックアップ用の機器として一般的によく使われるメディアのひとつです。大容量でコストパフォーマンスに優れています。一方、SSDは同じ容量でも価格は高めですが、軽量で読み書き速度が速く、消費電力が少ないのがメリットです。
予算を抑えて大容量のバックアップを取りたい場合はHDDを、時間短縮や持ち運びの軽さを重視する場合はSSDをおすすめします。
USBメモリ
USBメモリは比較的安価で手に入りやすく、小型で扱いやすいのが特徴です。手軽に使える一方で、紛失や盗難のリスク、長時間の放置によるデータ消失には注意が必要です。データを気軽に持ち運んだり、外出先でコピーする際に便利です。
NAS
NASはネットワーク(LAN)を利用するため、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットのデータも簡単に共有できます。データの加工や移動も手軽に行えるのが特徴です。ほかのメディアより高額ですが、安全で高機能、活用範囲が広いメリットがあります。
クラウド
クラウドは機器を用意する必要がなく、インターネット上のサービスを契約するだけで利用可能です。どこにいてもアクセスでき、故障の心配もないため安心です。一定容量までは無料で使えますが、容量を超えると有料になるので注意が必要です。
バックアップを効率的に取る方法
バックアップにかかる時間は、保存するデータの量によって大きく変わります。そのため、新しく更新されたデータのみをバックアップする方法がおすすめです。
まずは一度すべてのデータをバックアップして保存し、その後は変更や追加があった部分だけを保存するというやり方です。これにより、時間を大幅に短縮でき、保存するデータ容量も抑えられます。
また、パソコンを使用している間にバックアップを行うと、負荷がかかることがあります。そのため、パソコンを使っていない時間帯、例えば就寝中などにバックアップを取るのが望ましいです。
バックアップ機能のスケジュール設定を活用すれば、自動的にバックアップを行うことも可能です。パソコンを日常的に使うとデータは必ず増えていくため、定期的にバックアップを取ることが大切です。パソコンの故障やウイルス感染は予測できないため、毎日あるいは週に1回のバックアップを行いましょう。
まとめ
パソコン内の重要なデータを失わないために、バックアップをしっかり取っておくことは非常に重要です。バックアップがあれば、パソコンの故障で大切なデータやファイルが失われても、簡単に復元できます。難しい作業ではなく手軽に行えるうえ、すべてのデータをバックアップする時間がなくても、一部だけを保存することも可能です。パソコンの不具合や故障はいつ起こるかわからないため、日頃から定期的にバックアップを取る習慣をつけることが、大切なデータを守る秘訣です。


















